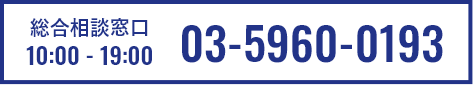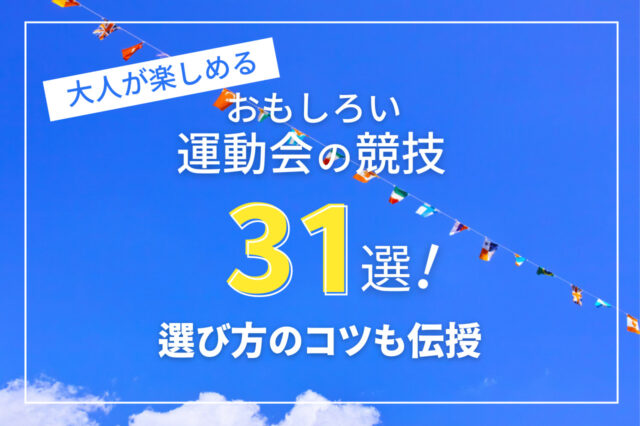チームビルディングの手法を20個解説|屋外スポーツも紹介!

企業力の底上げのためにチームビルディングを行いたいものの、どのように取り組むべきかお困りの方もいるでしょう。
本記事では、チームビルディングを目的としたアクティビティや手法を20個紹介します。記事を参考に、自社のチームビルディングにぜひ生かしてください。
社内イベント企画にお悩みの幹事様に、事例集などイベント会社のノウハウが詰まった資料を配布しています。
近年再注目を浴びる「社内運動会」。実施するメリットや、開催事例もご紹介します。
⇒ 無料で資料を受け取る
⇒ イベントや運動をする会場、探す前にプロに聞いてみませんか?
社内運動会の幹事さん必見!「社内運動会のメリットや失敗しないポイント」とは?
⇒ 無料のお役立ち資料をダウンロードする
【スポーツ系】チームビルディングの手法5選

スポーツを通じてチームビルディングできる手法を紹介します。
1.社内運動会

社員同士でチームを組んで行うのが社内運動会です。運動会はほとんどの方が学生時代に経験しているため、馴染みがある行事と言えるでしょう。各種目でチームメンバー同士協力し合うことで、チームビルディングの効果が期待できます。
学生時代に経験したことがある定番種目から、ニュースポーツを呼ばれる目新しい競技まで、運動会ではさまざまな種目を開催できます。
ここでは定番種目の運動会と、ユニークな種目を織り交ぜた運動会を実施するメリット、デメリットを併せて紹介します。
定番運動会を行うメリット
メリットは、老若男女が知っている競技が多いことです。簡単にルールを説明するだけで誰もが理解できる競技がほとんど。学生時代を思い出しながら全員が一体感を持って楽しめるでしょう。
定番運動会を行うデメリット
デメリットは、徒競争など運動神経が勝敗を左右する種目が多いことです。またほとんどの方に経験がある分、運動会がマンネリ化する可能性もあります。
ユニークな運動会をするメリット
これまで体験したことがない競技が多く、参加者の多くが新鮮な気持ちで運動会に参加できます。また、謎解きなどの頭脳を使う競技を盛り込むケースもあり、運動に苦手意識がある方でも参加しやすくできるでしょう。
ユニークな運動会をするデメリット
新種目である分、ルールを知らない方が多いため、丁寧に説明する必要があります。事前練習などを行わない場合、参加者はその場でルールを理解する必要があるため、難解なルールのスポーツは不向きでしょう。
株式会社IKUSAは、年間150以上の社内イベントを実施するイベントのプロフェッショナルです。企画から当日の運営まで一気通貫でプロデュースでき、ニュースポーツを取り入れた「NEW運動会」や歴史をモチーフにアレンジされた種目を楽しめる「戦国運動会」など、多種多様な社内運動会のアイデアをご提案します。
社内運動会の実施をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
社内運動会の幹事さん必見!「社内運動会のメリットや失敗しないポイント」とは?
⇒無料お役立ち資料を受け取る
2.ブラインドサッカー
ブラインドサッカーは、アイマスクをつけ、視界を遮った状態でプレイするサッカーです。健常者と視覚障がい者が一緒に楽しめるスポーツとして親しまれていますが、アイマスクを使用すれば障害の有無を問わず楽しめるスポーツです。
ブラインドサッカーでは、音のなる特殊なボールを使い、ゴールキーパーとコーラー(ゴールの後ろにいて、ゴールの位置と角度、距離を伝える役割)だけは目が見える状態でプレイします。フィールドプレーヤーは目が見えないため、チームメンバー同士で声を掛けることが大事です。自分がどんな状況か話したり、ゴールキーパーが選手にボールの位置を知らせたりすることで、他のメンバーが動きやすくなります。
一人ひとりが声をかけ合いゲームを進める必要があるため、高いチームビルディング効果が期待できるでしょう。
3.ドラゴンボート

縦長のボートを漕いでタイムを競う競技です。1チームにつき、10~20名程度の漕ぎ手、1名の舵取り役(舵をきって、船の方向を調整する人)とドラマー(太鼓などの打楽器を叩いて、漕ぎ手のリズムを取る人)がいます。
勝負のカギはメンバー間の連携です。いくら全力で漕いでも、漕ぎ手のリズムがバラバラだと、進むべき方向にボートが進みません。
ドラマーのリズムに合わせながら、波の状況や漕ぎ手の状態を見て一人ひとりが舵取りをします。チーム全員が息を合わせる経験を通じて、チームビルディングできます。
4.チャンバラ合戦

株式会社IKUSAが提供する「チャンバラ合戦」は、チームに分かれ、スポンジ製の刀で相手の腕についたボールを斬り合うアクティビティです。実戦前に必ずチーム内で作戦を話し合う時間が設けられ、立てた戦略を元にチーム一丸となって戦うことで、高いチームビルディング効果が期待できます。
チームごとのトーナメント形式のほか、チームの中で大将を決める大将戦、個人戦などさまざまなルールで楽しめます。体を動かしながらチームで一体感を育めるアクティビティをお探しの方はぜひ一度ご相談ください。
5.マラソン大会
マラソンは個人の努力もさることながら、完走という共通の目標をもち、成功体験を分かち合えるため、チームビルディングには最適です。
大会当日や本番までの練習期間で、お互いの様子やコンディションを配慮し合う機会も生まれ、自然とコミュニケーションを取る機会となるでしょう。
社内運動会の幹事さん必見!「社内運動会のメリットや失敗しないポイント」とは?⇒無料のお役立ち資料をダウンロードする
【交流系】チームビルディングの手法5選

対話や文化を通じてチームビルディングできる手法を紹介します。
1.ワールドカフェ

「カフェのようにリラックスできる空間の中でこそ生成的な話し合いが可能になる」という考えのもと、アメリカのアニータ・ブラウン氏とデイビッド・アイザックス氏が開発したこの手法は、世界各国で取り入れられています。
ワールドカフェでは4~5人が1つのテーブルを囲って、コーヒーなどを飲みながら話し合います。
対話の時間は4ラウンドに分かれ、1ラウンド目はチームでテーマについて話し合い、模造紙にまとめていきます。2ラウンド目は他チームの話し合いの様子を模造紙で確認します。3ラウンド目は初めのテーブルに戻り、他チームからの気づきをそれぞれ持ち寄ります。4ラウンド目はチームを超えて全体で話し合いアイデアを共有します。
自分の意見を口にし、相手の考えに耳を傾ける時間を通じてお互いを理解し合え、チームビルディングできます。
2.オープンスペーステクノロジー(OST)

1985年にハリソン・オーウェン氏によって提唱された手法で、コーヒーブレークがもたらす協働性をワークショップに取り入れる目的で開発されました。
ワールドカフェ同様に、自由な雰囲気の中で意見を出し合えます。最大の特徴は、参加者自身が議論したい課題を自ら提案し、自主的に話し合いを行う点です。OSTでは、大まかなテーマだけを決め、あとは参加者が自由にセッションを運営できます。仮に、テーマが「仕事」であれば、仕事に関するセッションを運営したい人を参加者の中から募ります。
Aさん「今後の仕事について」
Bさん「仕事とプライベートの関係性」
Cさん「仕事が与える影響」
Dさん「意義ある仕事とは」
Eさん「仕事をする理由」
セッションを運営しない人は、各自興味があるセッションへ参加して対話を行います。参加したいセッションが無い場合は、話し合わずに休憩スペースで過ごすことも認められています。
OSTでは、課題に対する貢献の仕方は個人に委ねられているため、関心が無かったら参加しなくて良いのが特徴です。このように自ら意思決定することにより、仕事でも意思決定力が高まるため、チームでの業務がスムーズになります。
3.ドラミング
チームでドラムを叩いて、音色を奏でるアクティビティです。海外でも取り組まれている活動で、過去には6,000人で行った記録もあります。ドラム未経験者でも参加できるため、経験の有無を問わずたくさんの人が参加できます。
ドラミングでは、上手に演奏するのではなく、他のメンバーのことを考えながら演奏することが大事です。自身がリズミカルに演奏できたとしても、他のメンバーとの音色がバラバラだと、音は不揃いになります。
そのため、自分がどのように演奏すればチームとしての演奏が良くなるか考えることが重要です。自分の音の奏で方を考えながら演奏することにより、チームビルディングの効果が期待できます。
4.バーベキュー

料理や食事を共にする機会を作るバーベキューは、自然なコミュニケーションを生み、チームビルディングイベントとして最適です。
カジュアルで楽しい雰囲気を醸成でき、形式ばらない会話が生まれるでしょう。また肉を焼いたり食器を片付けたり、参加者同士が役割分担を行うことで、チームワークを強化できます。
株式会社IKUSAは企業向けの出張バーベキューサービス「チームビルディングBBQ」を提供しています。企画や会場探し、食材の手配、撤収まで全てお任せできるサービスで、手間をかけずに本格的なバーベキューを楽しめます。
チームビルディングとしてバーベキューを取り入れたいと検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
5.ボランティア活動
企業としてボランティア活動に参加することもチームビルディングに最適です。共通の目的に向かって協力することで、チームに結束力と信頼感が生まれ、メンバー同士のコミュニケーションが改善されます。また社会貢献を通じて共感と感謝の気持ちが育まれ、チームの絆が深まるでしょう。
企業が参加できるボランティア活動として以下のアイデアが挙げられます。
- 地域清掃活動
- 植樹活動
- チャリティーイベントの企画
【ゲーム系】チームビルディングの手法10選

ゲームを通じてチームビルディングができる手法を紹介します。
1.コンセンサスゲーム

コンセンサスとは、「意見の一致」のこと。コンセンサスゲームは、チーム内で意見を一致させて、一つの解答を決めるゲームです。各チームに出題される問題には模範解答があり、その模範解答に出来るだけ近い解答を導き出す必要があります。
このゲームでは、違う意見を持っているメンバーそれぞれが、意見と交換し折り合いをつけるプロセスが求められます。そのため、相手を説得する力や、自分が譲歩するタイミングなどが重要になります。一連の交流を通じてチームビルディング効果が期待できるでしょう。
なお、代表的なコンセンサスゲームとしては、以下のようなものがあります。
株式会社IKUSAでは、物語を通じて複数人が合意形成する要点を学べる研修「合意形成研修コンセンサスゲーム」を提供しています。サバイバルのシーンを想定した3種類のストーリーから内容を選べ、社員のコミュニケーション力やグループの論理的思考力を高めながらチームビルディングできる研修です。
2.レゴ®シリアスプレイ®

レゴ社が開発したワークショップ型の研修プログラムです。お題に合わせて、自分の気持ちや状況をレゴブロックで表します。たとえば「今までで一番頑張ったこと」というお題であれば、レゴブロックを使って頑張ったことを表現し、その後、作品を通じてチーム内で、どのような気持ちで作ったのかを共有します。
チームで共有する中で、自分の気持ちに変化が現れたり、他の人の意見で共感できたりする箇所が現れ、チームビルディングにつながります。NASAやGoogleなど、有名企業でも導入されています。
またこの研修は公式のファシリテーターに進行してもらうことで十全な効果が期待できるとされています。
3.The Big Picture

各チームで作成した絵をつなぎ合わせて、1枚の巨大な絵を作成するアクティビティです。以下のような流れで進められます。
- どんな絵を作るかテーマを発表
- どの部分を描くか、グループごとに決める
- 各グループで作業に取り掛かる
- 仕上がった絵をつなぎ合わせて、1枚の巨大な絵が完成[
他のチームがどんな絵を描くか考えたり、完成図をイメージしたりしなければならないため、物事を俯瞰的に見る力が身につきます。さらに、1枚の巨大な絵を完成させるために、他のグループと共同して作業する感覚を持てるため、広い範囲でのチームビルディング効果が期待できるでしょう。仕事においても他部署に対する気遣いが出来るようになり、業務をスムーズにしてくれるでしょう。
4.ペーパータワー
ペーパータワーとは、A4用紙だけを使ってチームでより高いタワーを作るゲームです。制限時間内にどのように組み立てるかを話し合い、実践します。アイデアを交わし、役割分担しながらゲームを進めることで、コミュニケーションが改善されチームビルディングの効果が得られます。
ペーパータワーを実施した様子は以下の動画よりご覧いただけます。
5.マシュマロゲーム
マシュマロゲームは、パスタの乾麺とマスキングテープ、ひもを駆使してタワーを作り、頂上にマシュマロを載せたタワーを作るゲームです。4〜5人1組となり、制限時間内で組み立て方を話し合い、より高いタワーをチームで協力して作ります。
前に紹介したペーパータワーとルールは似ていますが、使える道具が増える分、アイデアが広がるでしょう。
ゲームの様子が動画でご覧いただけます。
6.宝探し
宝探しにチームで取り組むことで、協力してヒントを解読し目標を達成する過程でコミュニケーションが促進され、チームビルディング効果が期待できます。チーム対抗にすることで競争心が芽生え、チーム全体のエネルギーと団結力も向上するでしょう。
株式会社IKUSAは歴史をモチーフとした宝探しゲーム「戦国宝探し」を提供しています。宝の地図を手がかりに隠された宝を見つけ出します。謎の解読や探索を通じて、メンバー同士交流を深められるでしょう。
企業オリジナルの謎を仕掛けるアレンジもできます。企業色豊かなイベントを開催したいという際にもぜひご検討ください。
7.謎解き脱出ゲーム
謎解き脱出ゲームでは、参加者が協力して複雑な謎を解く過程を経験でき、コミュニケーション力やチームワークが向上します。制限時間内に脱出するというミッションを成功させることで達成感と共に結束力を育めるでしょう。
株式会社IKUSAが提供する「謎解き脱出ゲーム」は物語の主人公になる没入感を味わいながら、謎解き脱出ゲームを体感できます。ミステリーやSFなど、ストーリーの選択肢が豊富なため、メンバー全員が夢中になれる内容が見つかります。
謎解き脱出ゲームを社内研修に取り入れたいと検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
8.ノーカタカナゲーム
ノーカタカタゲームは、あるテーマについてカタカナ言葉を使わずに説明し、他のメンバーに伝えるゲームです。例えば「野球」であれば、「ボール」「バット」などの言葉は使えません。慎重に言葉を言い換えながら、適切に説明する能力が求められます。
メンバー同士、相手が何を伝えようとしているのか耳を傾け合います。ゲームでコミュニケーションを取りながら、相互理解を深められるでしょう。
9.王道当てゲーム
王道当てゲームは、一人回答者を決め、テーマに対する3 つの回答を用意してもらいます。例えば「味噌汁の具」であれば「豆腐」「ネギ」「なめこ」といったように決め、他のメンバーが回答者の答えを当てるゲームです。
ゲームを通じて相手の考え方や好みなどを知り、メンバー同士の距離感をより縮められるでしょう。
10.ワードウルフ
ワードウルフとは、少数派を会話の中で生まれる手がかりから推理していくゲームです。
メンバー一人ひとりにキーワードが渡される中で、一人だけ多数派とは違うキーワードを受け取ります。その人が「ワードウルフ」の役割です。キーワードを受け取った後、メンバー同士でそれについて会話をし、ワードウルフが誰かを探ります。ワードウルフが誰か当てることが多数派の勝ち、逃げ切ることができれば少数派(ワードウルフ)の勝ちです。
ゲームの進行に合わせて、自然な形で意見交換が促進され、チームの絆が強まり、チームビルディングを行えます。
まとめ

チームビルディングを行うことにより社員同士の連携が向上することで、社内での生産性がアップし、事業拡大にもつながります。今回紹介した20個の手法から、自社に合ったアイデアを取り入れて、チームビルディングに役立ててください。
全員が夢中になる、体験型の社内運動会。「社内運動会.com」は、参加者全員が没入して楽しめるチーム対抗型アクティビティ。運動を通じて自然にコミュニケーションが生まれ、部署や役職を超えた一体感を育みます。
競技だけでなく、演出・進行・装飾までトータルサポート。企業の目的や人数に合わせてカスタマイズできるため、
盛り上がりながらチームビルディングやエンゲージメント向上も実現できます。
⇒ 社内運動会 総合資料を無料で受け取る
⇒ 実際に行われた社内運動会の事例資料を無料で受け取る
参考サイト:
- ワールド・カフェとは?|WORLD CAFÉ.NET
- ラーニング・オーガニゼーション最新事例3:OST(Open Space Technology)|HUMAN VALUE
- コンセンサスゲーム:「無人島での出来事」のやり方|株式会社HEART QUAKE
- 合意形成研修コンセンサスゲーム|IKUSA
- なぜ世界一の玩具「レゴ®ブロック」が貴社の生産性を劇的に向上してくれるのか?|HELLO!
- リズムで心をひとつに!|DRUM CAFÉ JAPAN
- ブラインドサッカーのルール|特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会
- ドラゴンボートをはじめる|一般社団法人日本ドラゴンボート協会JDBA
- イベントからWEBマーケティングまで!|IKUSA