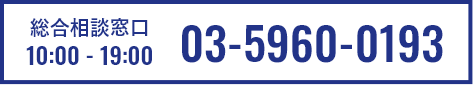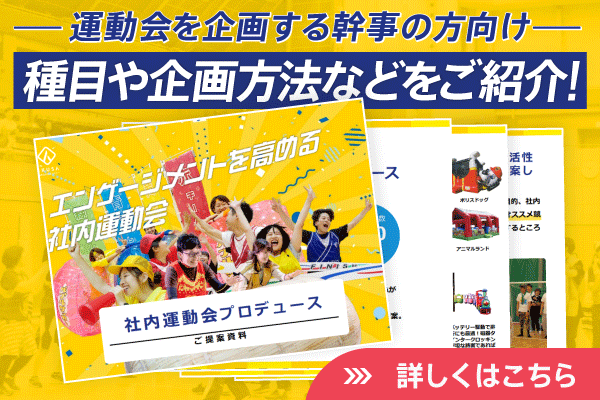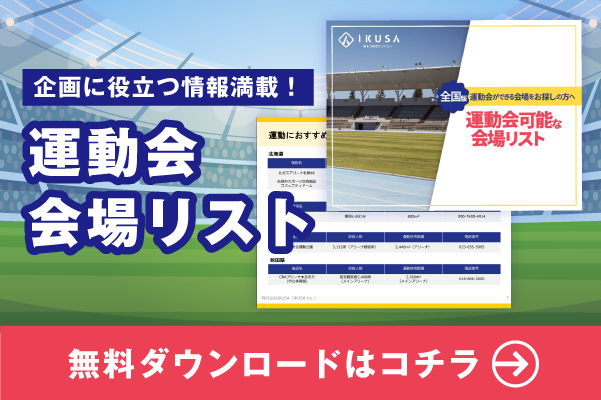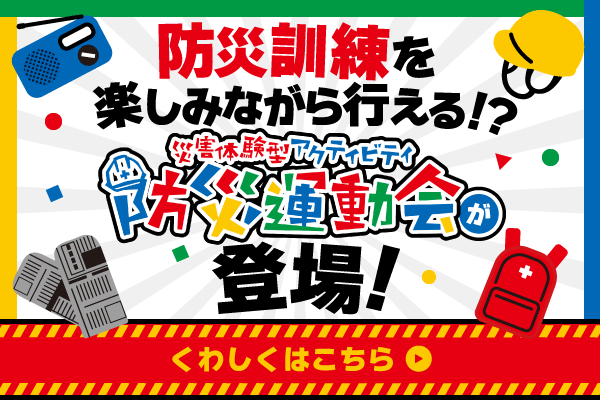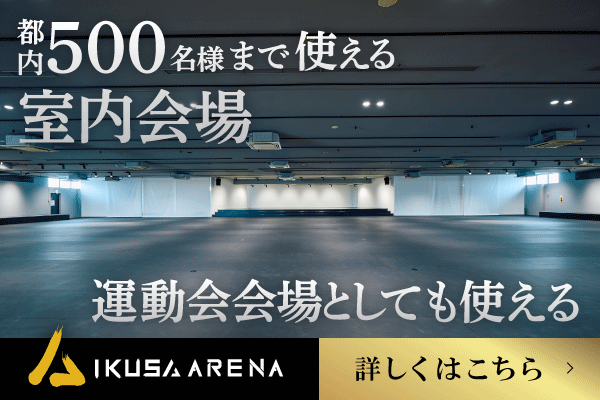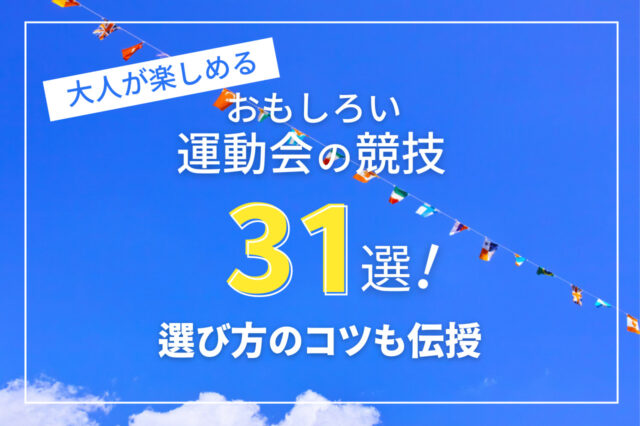社内運動会の企画アイデア15選!メリットや開催までの流れを解説

「社内運動会を計画・運営してほしい」と任されたものの、具体的な進め方や盛り上がる種目がわからず、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。近年、社員同士のつながりを深める手段として、社内運動会が再び注目されています。
この記事では、初めて幹事を担当する方でも迷わず準備を進められるよう、企画のアイデアから開催までの具体的な流れ、運営方法の種類までをわかりやすく解説します。
『社員の記憶に残る運動会にしたい』『今年は少し変わった企画に挑戦したい』。そんな幹事さんに定番とは一味違う、社員の記憶に残る運動会を企画するためのアイデア集を無料配布中。
なぜ今、社内運動会が重要?会社にもたらす効果

近年では、社内運動会を取り入れる会社が増えています。
その背景には、働き方の多様化により、社員同士のつながりが薄くなりつつあるという課題があります。社内運動会は、部署や役職の垣根を越えた交流を促し、会社の一体感を高める絶好の機会です。
普段の業務では見られない同僚の一面を知ることで、お互いの理解が深まり、より円滑な人間関係づくりにつながります。また、チームで力を合わせて目標を達成する経験は、協調性や連帯感を育み、会社への愛着や貢献意欲を高めるのにも効果的です。
心身のリフレッシュはもちろん、会社全体の活性化という観点からも、社内運動会は非常に重要なイベントと言えます。
社内運動会の企画アイデア15

ここからは、社内運動会におすすめする企画を15種類ご紹介します。「チームの結束力を高める協力型」「会場を盛り上げるおもしろ系」「頭を使う戦略系・謎解き系」「家族も一緒に楽しめるファミリー向け」の4つのカテゴリーに分けて解説しますので、運動会の目的や参加者に合わせて最適な種目を選んでください。
チームの団結力を高める協力型種目
チームの結束力を高めるには、全員で協力しなければクリアできない種目がおすすめです。共通の目標に向かって力を合わせることで、自然と会話が増え、一体感が醸成されます。
ここでは、チームの団結力を高める協力型種目をご紹介します。
大縄跳び
大縄跳びのルールは単純ですが、縄を回す人と跳ぶ人の呼吸をそろえ、「せーの!」と声を掛け合うことが成功するためのポイントです。練習を重ねるごとに一体感が高まり、本番で多く跳べたときの喜びは格別です。参加者だけでなく、見ている側も一体となって楽しめる、人気の高い競技です。
ムカデ競走
ムカデ競走は、複数人の足を紐で結び、息を合わせて前進する競技です。一人の動きがズレると、チームメンバー全員が転倒する可能性があるため、スピードよりも連携性が何よりも重要になります。「いーち、に、いーち、に」と声を合わせ、前の人の動きに合わせて進むことで、息の合った動きを作り出せます。
大玉送り
大玉送りは、直径1メートルほどの大玉をチーム全員で頭の上を転がして運ぶ協力型の競技です。運動の得意でない人も気軽に参加でき、世代を問わず楽しめます。
背の高さ順に並ぶといった列の作り方や、スムーズな受け渡しを指示するリーダー役の存在が勝敗を左右します。チームで戦略を練り、協力して大玉を運ぶ過程は、団結力を高めるのにぴったりです。
綱引き
綱引きで勝利するためには、力だけではなく、体重を後ろにかける姿勢や掛け声も重要となります。一本の綱をチーム全員で引くという行動が一体感を生み、勝っても負けても「全力を出し切った」という充実感や達成感を味わえるでしょう。
会場を盛り上げるおもしろ系種目
社内運動会を盛り上げるには、競技者だけでなく観客も一体となって楽しめる「おもしろ系種目」を取り入れるのがおすすめです。予測外の展開や、思わず笑ってしまうようなハプニングは、会場全体の雰囲気を和ませ、自然に会話を生み出します。
ここでは、会場を盛り上げるおもしろ系種目をご紹介します。
借り人競走
借り人競走は、「〇〇部長」「メガネをかけた人」といったお題に合う人を観客席から探し出し、一緒にゴールを目指す競技です。お題のカードを引くまで誰が対象になるかわからないドキドキ感が、会場全体を盛り上げます。普段あまり話さない人とも自然に関わるきっかけになり、社内の交流を活性化させる効果もあります。
障害物リレー
障害物リレーは、網くぐりや平均台、パン食い競争など、さまざまな課題をクリアしながらゴールを目指す競技です。器用さや運が求められる障害物を盛り込むことで、誰にでも勝利するチャンスが生まれます。チームでバトンをつなぎながら、次々と障害物に挑戦する姿は、見ているだけでも楽しめ、会場が一体となって盛り上がるでしょう。
借り物競走
借り物競走は、カードに書かれた「モノ」を会場内から探し出し、ゴールを目指す競技です。お題には「ハンカチ」のような身近なものから、「二つ折りの携帯電話(ガラケー)」のように探すのが難しいものまで登場します。周囲の人に声をかけて協力をお願いする中で、自然に会話が生まれ、チームや部署を越えた交流が活発になります。
体を動かしながら頭を使う戦略系・謎解き系種目
運動神経や体力だけでなく、知力や戦略が問われる種目を取り入れると、運動が苦手な人でもより楽しめます。チームで知恵を出し合い、作戦を練る過程は、論理的思考力や問題解決能力を育むのにも絶好の機会です。
ここでは、体を動かしながら頭を使う戦略系・謎解き系種目をご紹介します。
チャンバラ合戦
チャンバラ合戦は、スポンジ製の刀で相手の腕についたボール(命)を落とし合うアクティビティです。体力や運動神経よりも、チームでの作戦が勝利を目指す上で重要であり、年齢や世代を問わず誰でも楽しめます。
合戦前にチームで行う「軍議」と呼ばれる作戦で、誰が攻めて誰が守るのか、どのような陣形で戦うのかをチームで話し合い、連携して戦います。楽しみながら、関係を深められる点も魅力です。
防災借り物競争
防災借り物競争は、「災害発生直後」という設定の中で、身の回りにある物を使って応急処置などのお題をクリアする競技です。例えば、「骨折した人を運ぶ」というお題では、物干し竿や毛布を使って担架を作るなど、発想力とチームでの協力が試されます。
楽しみながら災害時に役立つ知識やチームでの共助の重要性を学べる、社会的にも意義のある種目です。
【オンライン】リモ謎
リモ謎は、オンライン会議ツールを活用し、チームで協力して謎を解くオンライン脱出ゲームです。リモートワークが中心の会社や、複数の拠点を持つ会社でも、場所の制約なく一体感を得られます。誰か一人のひらめきが謎を解くヒントになることもあり、活発なコミュニケーションが欠かせません。
家族も一緒に楽しめるファミリー向け種目
社員の家族を招待する運動会では、小さなお子さんから年配の方まで、誰もが安心して楽しめる種目を取り入れるのが理想です。家族も一緒に参加することで、家族の会社への理解を深められるだけでなく、職場全体の和やかな雰囲気づくりにもつながります。
ここでは、幅広い世代で楽しめるファミリー向け種目をご紹介します。
玉入れ
玉入れは、ルールが単純で、小さな子どもから大人まで誰でも参加できる運動会の定番競技です。たくさんの玉が空に舞う様子は、見た目にも華やかで、会場の雰囲気を盛り上げてくれます。小さな子どもが参加する場合には、背の低いカゴを用意するなど少しルールを工夫するだけで、さらに全員が楽しめるでしょう。
キャタピラ競走
キャタピラ競争は、段ボールなどで作ったキャタピラの中に入り、ハイハイで進む競技です。前が見えにくく、まっすぐ進むだけでも苦労します。参加者がハイハイで一生懸命に進む姿に、会場から自然と笑顔がこぼれます。
ハイハイができれば小さなお子さんでも参加できるため、ファミリー向けの種目に向いています。親子で一つの大きなキャタピラに入って協力して進むなど、アレンジを加えるのもおすすめです。
フラフープリレー
フラフープリレーは、フラフープを腰の位置に持ちながら走るリレー競技です。チームごとに1つのフラフープをバトン代わりに使い、次の走者へつないでいきます。ルールは単純ですが、手を振らずに走る姿勢に慣れることが早く走るポイントです。
一つのフラフープに二人で入って走るというアレンジを加えれば、息を合わせて進む必要が出るため、チームワークを育むことができます。
バケツリレー
バケツリレーは、メンバーが一列に並んでバケツを次々と手渡し、バケツが端まで渡り切るまでの時間を競う競技です。もともとは防災訓練から生まれた種目で、隣の人と呼吸を合わせることが何よりも大切になります。
水の代わりにボールを使用すれば、服が濡れる心配はありません。チームで効率よくバケツを運ぶためには、並び順を工夫するなどの作戦も求められます。
社内運動会の計画から開催までの流れ

社内運動会の準備を行き当たりばったりで進めてしまうと、当日の運営が混乱したり、参加者の満足度が低下したりする恐れがあります。後悔しないためにも、開催までの流れを知り、計画的に準備を進めましょう。
ここでは、運動会の計画から開催当日までの流れを5つの段階に分けて紹介します。
- 目的を明確にし、運営体制を整える
- 会場・日程・予算を決定する
- プログラムと競技内容を企画する
- 社員に告知する
- 会場の設営を行う
1.目的を明確にし、運営体制を整える
まずは「何のために社内運動会を開催するのか」という目的を明確にします。目的によって、競技の内容やプログラムの構成が大きく変わるため、「社員同士のつながりを深める」「社員やその家族に感謝を伝える」など、具体的な目的を設定しましょう。
目的が定まったら、運動会の運営を担当する実行委員会や担当チームを立ち上げます。各部署からメンバーを募集するなどして、全社的な協力体制を築きましょう。
2.会場・日程・予算を決定する
運営体制が整ったら、次に具体的な計画を立てていきます。参加予定人数や実施したい競技内容に合わせて、適切な広さの会場を確保します。体育館、グラウンド、イベントホールなど、選択肢はさまざまです。アクセスの良さや付帯設備、天候への備えなども考慮して選定しましょう。
会場の候補が決まったら、開催日を検討します。会社の繁忙期を避け、多くの社員が参加しやすい日時を選びましょう。同時に、会場費、備品レンタル費、景品代、飲食代など、必要な費用を洗い出し、予算を確保します。
3.プログラムと競技内容を企画する
会場と日程、予算の目処が立ったら、運動会の中心となるプログラムと競技内容を決めていきます。設定した運動会の目的に立ち返り、目的を達成できるような内容にすることがポイントです。
例えば、チームワークの強化が目的なら大縄跳びや綱引きなどの協力型種目を、交流促進が目的なら借り人競走のような観客を巻き込む種目を取り入れるとよいでしょう。運動量のバランスや休憩時間も考慮しながら、誰もが参加しやすいプログラムを作成することも大切です。
4.社員に告知する
プログラムが完成したら、社員への告知を行います。単に日程と場所を伝えるだけでなく、運動会の目的や見どころ、用意している景品などを紹介し、参加意欲を高める工夫を凝らしましょう。
社内報やポスター、メールなどを活用し、開催日まで定期的に情報を発信することで、社員の期待感を高められます。参加申し込みの締め切りを明確にし、出欠を早めに把握しておくことも、円滑な運営のために欠かせません。
5.会場の設営を行う
開催当日は、参加者が快適に過ごせるよう、会場の設営は念入りに行いましょう。受付、救護室、更衣室、トイレなどの場所をわかりやすく表示し、競技エリアのライン引きや備品の配置などをプログラムに合わせて準備します。
当日の役割分担を運営スタッフ全員で再確認し、開会式から閉会式までの流れをシミュレーションしておくと、予期せぬトラブルが起きても落ち着いて対処できます。しっかりと準備を整え、参加者全員を迎えましょう。
社内運動会の運営、自社で行う?プロに依頼する?
社内運動会の運営方法には、すべてを自社で行う方法と、計画・運営を専門のイベント会社に依頼する方法の2つがあります。どちらの方法にもメリット・デメリットがあるため、自社の状況や目的に合わせて選びましょう。
自社で運営するメリット・デメリット
自社で運営する最大のメリットは、費用を抑えられる点と、社員が主体的に関わることで一体感が生まれやすい点です。計画から運営までを社員が担当した経験は、社内のノウハウ蓄積にもつながります。
一方で、担当者の業務負担が大幅に増加する点はデメリットです。通常業務と並行して準備を進める必要があり、内容がマンネリ化したり、当日のトラブル対応に追われたりするリスクもあります。
メリット | デメリット |
費用を安く抑えられる 社員の一体感を醸成しやすい 運営ノウハウが社内に蓄積される | 担当者の業務負担が大きい 内容がマンネリ化しやすい 安全管理やトラブル対応の専門知識が不足しがち |
イベント会社に依頼するメリット・デメリット
イベント会社に依頼する最大のメリットは、計画・運営にかかる担当者の負担を大幅に減らせることです。プロならではの面白いプログラム提案や、会場・備品の手配、当日の司会進行まで一括して任せられるため、質の高い運動会を実現できます。
一方で、委託費用がかかる点と、自社の文化や意図を十分に伝えられない場合にイメージのズレが生じる可能性がある点に注意が必要です。
メリット | デメリット |
担当者の負担を大幅に軽減できる プロのノウハウで運動会の質が向上する 会場や備品の手配、当日の運営まで任せられる 安全管理やトラブル対応も安心 | 委託費用がかかる 自社の意図が伝わりにくい可能性がある 社内に運営ノウハウが蓄積されにくい |
社内運動会に関するよくある質問

ここでは、社内運動会の幹事が抱えがちな疑問をまとめました。
参加率を上げるための工夫はありますか?
参加率を上げるためには、「参加したい」と思わせる工夫と、参加しやすい環境づくりが重要です。豪華景品を用意することのほか、誰でも楽しめる競技を取り入れたり、余裕を持って告知したりすることも効果的です。
運動会が盛り上がる景品の選び方を教えてください。
景品を選ぶ際は、多くの人が「欲しい」と思うものと、笑いを誘う面白いものをバランスよく揃えることがおすすめです。優勝チームには最新の家電や旅行券といった豪華景品を、個人のMVP賞には高級食材などを用意すると喜ばれるでしょう。また、参加賞や残念賞として、面白いパッケージのお菓子や少し変わった日用品などを用意すると、会場の雰囲気が一段と和やかになります。
雨天の場合の対策はどうすればよいですか?
屋外で運動会を計画する場合、雨天時の対応はあらかじめ決めておく必要があります。対応策としては、「延期する」または「屋内会場へ切り替える」の2つが一般的です。
延期する場合は、あらかじめ予備日を設定し、会場を確保しておくのがおすすめです。屋内会場へ切り替える場合は、雨天時のプログラムを準備しておきましょう。
まとめ

この記事では、社内運動会の企画アイデアから、計画・開催までの流れ、運営方法について幅広く解説しました。社内運動会は、会社の一体感を高め、交流を活性化させるための重要なイベントです。
初めて幹事を任された方は、何から手をつけてよいかわからず不安に思うかもしれませんが、今回ご紹介した流れに沿って一つひとつ準備を進めれば、きっと素晴らしい運動会を実現できるはずです。定番の競技から面白い競技まで、自社の目的に合ったプログラムを用意し、社員の記憶に残る一日にしてください。
ユニークな運動会のアイデアは見つかりましたか?この記事で紹介した内容に加え、企画書作成のポイントや、過去の成功事例をまとめた【ユニーク運動会ガイド】を無料で提供中。

この記事を書いた人
社内運動会.com